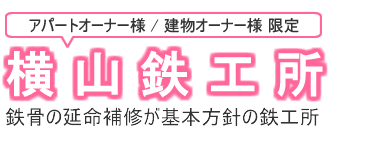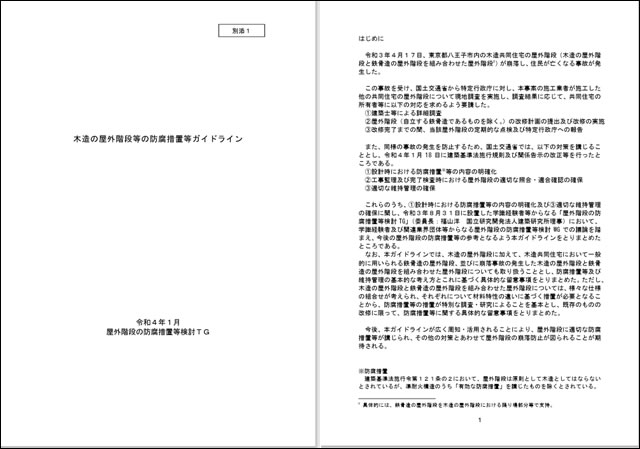この記事を読んでいただきたい方:
所有する建物の鉄骨階段や廊下の錆び腐食でお悩みのオーナー様、国土交通省「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン」の内容や具体的な防腐措置の施工方法を知りたいオーナー様向けの記事です。
目次
八王子のアパート階段崩落事故をきっかけに広がる対策
2021年(令和3年)に東京都八王子市で起きたアパートの階段崩落事故は、テレビでも大きく報じられました。この事故は、階段接合部が腐食により外れたことで居住者の転落死亡を招いてしまった構造欠陥トラブルです。この施工会社は書類送検され、建物賃貸業界に衝撃が走りました。私どもも当時は報道メディアの取材があったり、事故関連の建物オーナー様のご相談が多く、目まぐるしい日々でした。
参考動画:八王子アパート階段崩落転落死 施工会社の元会長を書類送検|TBS NEWS DIG
事故についてもう少し具体的に書くと、崩落が起きた建物の鉄骨階段(鉄骨)は、踊り場(木材)と別資材の構造になっており、踊り場下地の腐食が引き金となって接合部(ビスだけ)が外れた・・という経緯です。
このような事故は珍しいことではなく、検索すると多くの事例が見つかります。こうした事故は、建物の所有者であるオーナー様に大きな賠償責任を問うことにもつながります。
参考:老朽化が原因か アパート階段踊り場崩落事故 1人は頭を強く打って死亡(FNN)
参考:アパートの廊下が崩落、3m落下した2人重傷(読売新聞オンライン)
国土交通省が「維持工事ガイドライン」提唱
八王子の事故を受けて、国土交通省は2022年(令和4年)に「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン」を提唱しました。このガイドラインは、建物の維持管理における防腐措置の基本的な考え方や留意点を詳細に示しており、外部に設置された鉄骨階段や廊下を風雨による腐食から守るための重要な指針となっています。
参考:木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン(国土交通省)
外部にある鉄骨設備(階段、廊下、ベランダなど)は、風雨に晒され続けているので腐食(経年老朽化)は避けられません。
たまに「うちはアルミだから大丈夫」という声を聞きますが、懸念箇所や対応策が異なるだけで放置すれば強度懸念が生じることは資材を問わず同じです。
鉄骨設備に話を戻します。
今回の事故によって、劣化による強度低下を防ぐための予防策として、鉄骨設備の防腐措置の必要性が広く認識されるようになりました。
鉄骨設備の防腐措置(工事タイミングと断面解説)
防腐措置は鉄骨設備を理解するのに必要な知識であり、腐食トラブルの傾向と対策を把握することに繋がります。


防腐措置が施されていないアパートの廊下では、床面のモルタルにヒビが入り、そこから雨水が内部に浸水して鉄骨を腐食させてしまいます。以下のような症状が見られる場合は、専門業者に相談するタイミングといえます。
- 床面モルタルに隙間やヒビがある
- 廊下を下から見たときに、鉄部分がサビている
次に、廊下の断面構造を解説します。
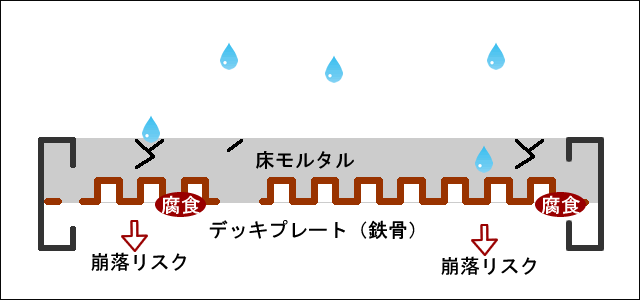
廊下の断面構造です。「上半分がモルタル、下半分が鉄骨」で構成されています。モルタルが経年劣化してくるとヒビや隙間から浸水が始まって、下にある鉄骨に湿気が停滞、腐食が始まります。最終的にはモルタルを支えきれなくなり、崩落事故の要件となります。
防腐措置の工事実例
工事は以下の流れで進めます。
- 鉄骨補強工事: 腐食状況に応じて強度を失った鉄骨構造の補強を行います。新たな鉄フレームを増設したり、弱っている部位の部分交換、耐水工事のための下地工事も完了させます。
- 防腐対象の下地補正:腐食の原因となる床モルタルのヒビ割れや隙間を埋める作業を行います。水性エポキシ材やカチオン、パテなどを用いて、このあとの長尺シート敷設の下地補正をします。
- 長尺シートの敷設: 床面への浸水を物理的に抑止するため、製品としての耐久性も高い長尺シートを敷設します。強力な耐水効果が生まれ、防腐措置が完了します。
1.鉄骨補強工事

廊下のデッキプレート(床を支える鉄部)を交換するような派手な工事はできないので、プレートの下に新たな鉄骨構造を増設して強度復旧をします。
鉄骨補強作業は、溶接火の粉の飛散、切断騒音、解体粉じんが発生します。必ず事前に工事案内をするのですが、居住者様の生活を停めることはできないので利用制限がほぼ出ないように安全誘導や作業段取りの管理など工夫します。
2.防腐対象の下地補正

経年劣化した床モルタルの弱っている部位(ヒビ割れや不自然な隙間)を水性エポキシなどで埋めつつ「長尺シート(耐水資材)」が敷設できるように準備をします。
長尺シートがモルタル面にしっかり密着されることが大切で、シートを敷いたあとには見えなくなってしまうところなので慎重に行います。記録写真も残しておきます。
3.長尺シートの敷設

下地補正が終わったら長尺シートを敷設します。写真は「大きなシートを縦半分に折っている状態」です。理由は居住者様の通行スペースを確保しながら作業するためです。
また、モルタル劣化は、建物側のキワや排水路のキワに強く出やすい(ヒビが生じて湿気が多く残ってコケが生えていたりする)ので、長尺シートを敷く前に「線防水」という下処理をすることがあります。線防水については「モルタル面の耐水事情のページ」の中で解説しています。

長尺シートが敷設されました。シート端部のコーキング処理も済ませて耐水効果を得ました。防腐措置完了しました。
防腐措置(耐水)の一般化に向けて
八王子の事故をきっかけに、国がガイドラインを提唱したことで、外部階段や廊下、ベランダなどの外部鉄骨設備の維持管理において、防腐措置の重要性が広く知られるようになりました。
単に「溶接して終わり」「塗装して終わり」ではなく、長尺シートなどで耐水性を得ることで、今回解説しました防腐措置が完了します。
腐食鉄骨を交換しないで延命補修をして防腐措置をするという行為は、「虫歯を抜かない(インプラントしない)で、深刻なところを治療したら、銀歯を被せる」というイメージでお話するとご理解いただけることが多いです。弊社は直接施工店なのでお気軽にお問い合わせください。
2023年の追記:長尺シートは資本的支出扱い?
追記です(2023年11月)。
今回の工事で敷設する長尺シート敷設の費用は、税法上「建物の資産価値を高める資本的支出」と見なされるケースが多く、修繕費として計上できない場合があります。
既存資産が法定耐用年数を超えるほどの工事をすると修繕費にはならないという見解が一般的なようですが、国土交通省が維持管理手段として推奨しているにもかかわらず、税務上は修繕費として認められないという側面は、オーナー様の間で議論が続いています。
要約Q&A
Q:八王子の階段転落事故の原因は?
A:鉄骨階段周囲の設備との接合不良です。腐食リスクの軽視、放置が招いた構造トラブルです
Q:木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドラインとは?
A:八王子事故をきっかけにに国土交通省が2022年(令和4年)に発布した設備メンテナンスのためのガイドライン資料です
Q:鉄骨設備の防腐措置とは?
A:鉄骨(特に他資材と一体となっている鉄骨)構造への浸水(湿気)リスクを抑止するために行う補修工事です
Q:防腐措置はDIYで可能?
A:腐食原因を把握しつつの作業なのでDIYはお勧めしません。モルタル面にヒビや不自然な隙間などが生じたら業者に相談してください
Q:長尺シートは追徴課税の対象になるの?
A:修繕費(経費)として計上できない理由は「既存資材と異なる資材で補修をしたとき」に指摘されることがあります。つまり、敷かれた長尺シートの張り替えは経費となります
Q:入居者様から非破壊検査をすべきと請求をされました
A:オーナー様には、アパートを使用収益に適するよう維持する義務はあります(民法606条)が、非破壊検査を必ず行うような法的義務はありません。また、非破壊検査は実施前提のハードルが高く、実施しても定量的な判断や解決策が出せるか疑問です