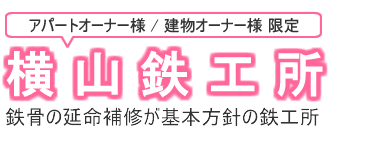この記事を読んでいただきたい方:
鉄骨階段の腐食について「延命補修」という方法があるらしいけど本当に大丈夫?工事で失敗しないためにメリットだけでなくデメリットも正直に知りたいと調べているオーナー様向けの記事です。

オーナー様には「交換or補修」という選択肢があります

鉄骨階段や廊下、ベランダ。錆びや腐食を見つけると「交換しないと危険かも・・」と不安になりますよね。業者に相談すれば「設備を新調しましょう」と提案されることが多いですし、解決策として間違っていません。その方が確実な安全性を得られるからです。
しかし、決済するオーナー様の中にも事情があります。例えば「あと15年くらいで建物を建て替える予定なのに、30年以上もつ新品の階段ができたら、損をした気分になってしまう」と、築古物件では寿命の逆転現象が起きてしまうのです。

そこで、上記の「いいとこどり」として有効なのが、既存の鉄骨を活かして強度を回復させる延命補修です。一定の安全性を確保でき、コストを大幅に抑えられるのが魅力ですが、万能ではありません。費用を抑える代わりに、いくつかの「副作用(妥協点)」があります。
鉄骨階段の延命補修を決めたときに、後悔をしないため、延命補修で達成できること、できないことを解説します。オーナー様の参考情報になれたら幸いです。
延命補修の主目的は「安全性」の確保

延命補修の目的は、鉄骨強度不安による人的被害リスクを抑止することです。オーナー様にとって、「短納期・低コスト」で安全性を確保できる有効策となります。
その仕組みは、既存鉄骨の構造を起点とすることで、使用鋼材量を減らして、優先順位をつけて溶接補強を行うことで、資材費や人件費を節約することにあります。
そもそも鉄は自然の素材なので、経年と合わせて酸化して強度を失っていきます。既存設備を継続利用するため、交換工事のような抜本的な解決ではなく、「暫定補強」「延命補強」で、一定の安全性を確保することが、延命工事の目標です。
参考:築古オーナーが知るべき「工作物責任」(楽待 不動産投資新聞)
延命補修の副作用。~クリアできないこと3点~

(1)塗膜の凸凹な仕上がり
延命補修作業の下準備となるケレン作業(鉄表面の錆びや、機能不全の塗膜を削り取る作業)をすると、「活膜」と呼ばれる密着したままの古い塗膜が残ります。この結果、仕上げ塗装をしたときクレーターのような凸凹な仕上がりになることがあります。新品と比べて美観をやや損ないますが延命効果に影響はありません。

(2)鉄骨内側や隙間から錆び垂れが出る可能性
延命補修が「既存鉄部を残しながら補強する」という特性上、既存鉄骨の内部深くから染み出る錆び垂れや、溶接接合点からの錆び垂れが、早いと工事後数ヶ月で出てくる可能性があります。しかしながら、上記の問題は補修工事の効果を損なうものではありません。
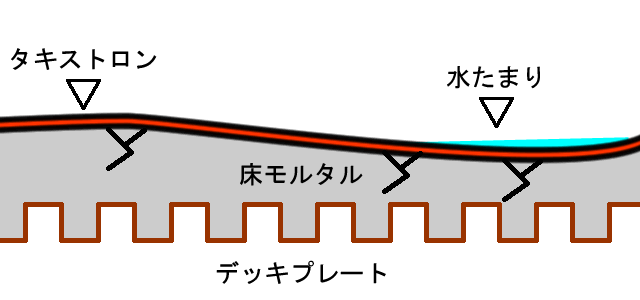
(3)耐水作業後の水たまりの可能性
延命補修で耐水作業(長尺シート)を施工したとき、雨天後に浸水先を失った雨水がしばらく床面に残ることがあります。
理由は、築年数のある建物の場合、床面に微妙な歪みや凹凸があることが多いのですが、長尺シートはこの床面形状をそのままトレースして敷かれます。結果として、雨が降った後に水が流れきらず、低い部分に水たまりが残ってしまうことがあります。
この場合でも、ホウキでさっと掃いたり、自然乾燥を待つことでクリアされますし、水たまりは耐水が成功している証拠でもあります。
参考:長尺シートの水たまりを解説

いかがでしたでしょか。延命補修工事を請け負う業者として率直にお伝えしてみました。
延命補修は、既存の設備に手を加えて寿命を延ばす対症療法で、建築セオリーとはやや方向性が異なる工事です。美観を維持ができないことは、安全性とコスト節約を確保するためのトレードオフとご理解いただければ、オーナー様と弊社はベストマッチな関係となります。
鉄骨の延命補修はお気軽にご相談ください。
要約Q&A
Q:鉄骨の延命補修を短納期、低コストにできる仕組みは?
A:既存構造を残して作業をすることで鋼材費を絞り、優先順位を絞って作業することで人件費を節約して、低コストの工事を実現します
Q:鉄骨の延命補修の弱みは?
A:既存構造を残して作業をすることで、塗装仕上がりや耐水仕上がりが「それなり」になります
Q:交換工事と延命補修の費用差の目安は?
A:工事ボリュームで変動しますが、おおよそ交換工事の3分の1から半額で達成できなければ、延命補修の意味がないと考えています