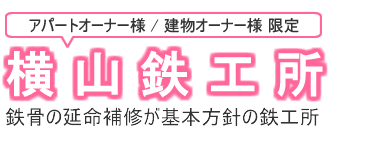この記事を読んでいただきたい方:
ご自宅やアパートの鉄骨バルコニーが古くなってきたオーナー様、床がふわふわする、手すりのサビがひどいなど、具体的な症状にお困りのオーナー様、バルコニーの交換は費用が高いと感じ、修理で済ませたいとお考えのオーナー様に延命補修の選択肢をご提示する記事です。

「バルコニーの床が歩くとギシギシと音がする」「手すりが錆びてボロボロなので、もたれるのが怖い・・」 このような症状、見て見ぬふりをしていませんか? それは、鉄骨の腐食が進んでいる危険なサインかもしれません。
放置すれば、床が抜け落ちるなどの重大な転落事故につながる恐れもあります。しかし、すぐに「交換」を考える必要はありません。適切な補修を行えば、今のバルコニーの寿命を15年以上使えるかもしれません。
この記事では、鉄骨バルコニーの腐食修理について、危険なサインから具体的な補修方法、費用の考え方までを分かりやすく解説します。
目次
自分でチェック!バルコニー腐食の危機レベル

オーナー様がご自身でチェックする項目は下記です。不安が当てはまったら、業者による点検をおすすめします。
- 床がふわふわする、きしむ:
床を支える鉄骨が腐食し、強度を失っている可能性があります - 手すりや柱の根元が錆びている:
塗装が剥がれ、内部の鉄骨まで腐食が進行しているサインです - サビ垂れ(汁)が出ている:
鉄骨が腐食して流れ出たもので、隠蔽部の強度低下の可能性があります - 床の「すのこ」が割れたり沈んだりしている:
すのこ自体の劣化、また、支える鉄骨にも問題が及んでいる可能性があります
これらの症状を放置すると、バルコニーの強度が著しく低下し、最悪の場合、床の崩落や手すりの脱落といった重大事故を引き起こす危険性があります。
下記の資料は、床抜けではありませんが、鉄骨廊下の床が抜けた事故についても記載されているものです。「アパートの2階外廊下の床が抜け落ち、引越し業者2名が1階に落下、重傷。軽量鉄骨造の外廊下の床材取付部の腐食が原因と推定」とあります。
参考:特定行政庁より報告を受けた建築物事故について:国土交通省
実践:鉄骨バルコニーの延命補修工事~鉄骨編~



腐食の状況に応じて、必要な部分だけを的確に修理することで、コストを抑えながら安全性を回復させることができます。従来の鉄骨を再利用しつつ、特に腐食がひどい箇所をピンポイントで交換していきます。

手すりの腐食は、見た目が悪いだけでなく、体重をかけた際の転落リスクに直結します。腐食がひどい部分をカットして取り除き、新しい鉄骨を溶接してつなぎ合わせることで、新品同様の強度を取り戻します。

バルコニーの床がフワフワしたりギシギシする理由は、床を支える鉄フレーム(根太、梁)が腐食している可能性が高いからです。
そこで、新たな鉄骨を増設したり、梁を交換したりして溶接で固定します。これにより、バルコニー全体の剛性に向上します。バルコニー利用時の不安な沈み込みや揺れも当然なくなります。
鉄骨の補強が終わったら塗装をして、塗膜コーティング完了。これは単なる化粧直しではありません。鉄骨を雨や酸素から守る強力なバリア(塗膜)を形成し、再度の腐食を抑止するための重要な工程です。
実践:鉄骨バルコニーの延命補修工事~スノコ編~

上の写真は、床すのこを撤去して、骨組みが見えている状態です。

老朽化した「すのこ」を新しいものに交換します。見た目が美しくなるのはもちろん、足元の安全性が格段に向上します。
これで、鉄骨バルコニーの延命補修は完了です。
気になる工事費用について

鉄骨バルコニーの修理費用は、腐食の進行度合い、バルコニーの大きさ、構造など、現場の状況によって大きく変動するため、定価がありません。
例えば、手すりの一部補修で済む場合と、床を支える骨組みから大規模に補強する場合とでは、費用が大きく異なります。そのため、まずは現場を調査し、どこにどのような補修が必要か、どこまでを補修範囲にするかをオーナー様とお打合せをして、打合せ通りの見積もりを作成する必要があります。
まとめ:交換と補修、なにが違う?メリット・デメリット


老朽化した鉄骨バルコニーの対処を相談された業者としては、一般的には交換工事がセオリーです。安全性を確約できる解決策だからです。
ただ、建物の維持年数から、交換に踏み切るのを躊躇されるご事情も現実としてあります。
弊社の延命補修は、その「折衷案」という形で延命補修の選択肢をご提案いたします(補修不可能なほど腐食している場合はご提案はいたしません)。
交換工事と延命工事の違いを、メリットデメリットで分けると下記です。
交換工事:高額、交換時にバルコニーが使えない、長寿命の安全性
延命工事:交換と比べてコスト安、バルコニーが使えない時間が短い、あくまで対処療法
資産価値を維持できる解決方針はオーナー様次第です。ただ確実にいえるのは、建物の維持年数が10年前後であった場合は、延命修理は賢い選択肢になります。
「うちのバルコニーもそろそろ危ないかも…」
そう感じたら、手遅れになる前に、鉄骨バルコニーの延命修理はお気軽にご相談ください。
【関連記事】
鉄骨バルコニーの補修工事例を以下でもご紹介しております。
要約Q&A
Q:自分でチェックできる、鉄骨バルコニーの危険なサイン(症状)は何ですか?
A:以下の4つの症状が見られたら危険なサインです。
- 床が歩くと「ふわふわ」したり、「きしむ」音がする。
- 手すりや柱の根元が錆びている。
- 茶色いサビ汁が出ている。
- 床の「すのこ」が割れたり、部分的に沈んだりしている。
Q:「交換工事」と「延命補修」の違いは何ですか?
A:端的にいえば、以下の通りです。
- 交換工事:
- メリット: 長期間にわたる高い安全性が確保できる。
- デメリット: 費用が高額になり、工事期間も長い。
- 延命補修:
- メリット: 交換に比べて費用を安く抑えられ、工事期間も短い。
- デメリット: あくまで対処療法であり、交換ほどの長期的な耐久性はない。
Q:鉄骨バルコニーの腐食を放置するとどうなりますか?
A:腐食を放置すると鉄骨の強度が低下し、最終的には、床が抜け落ちたり手すりが脱落したりする、人的被害のリスク要件を満たします
Q:古くなった鉄骨バルコニーは交換するしかないの?
A:いいえ、必ずしも交換が必要なわけではありません。腐食の程度によっては、交換よりもコストを抑えられる「延命補修」という方法で修理し、安全に使える期間を15年以上延ばすことも可能です
Q:どのような場合に「延命補修」がおすすめですか?
A:例えば、建物の残りの寿命が10年前後である場合や、交換工事ほどの費用はかけられないが、当面の安全性を確保したい場合に「延命補修」は賢い選択肢となります