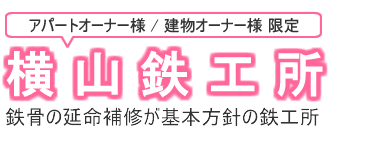この記事を読んでいただきたい方:
自宅やアパートの鉄骨ベランダの錆び問題に直面。しかし交換工事では費用や手間、入居者様対応など現実的な制約もあるため、最適な落とし所(延命補強策)を探している方。もしくは補強という選択肢が自分にとって有効かを模索したい方にお勧めの記事です。

鉄骨の土台が腐食し安全性に不安があるものの、全面交換が困難な場合にはどんな解決方法があるでしょうか。特にベランダや廊下、階段などの構造を支える鉄骨が錆びて経年劣化している場合は迅速かつ最適解な判断が求められます。
今回の記事では、鉄骨の土台を交換せずに補強する方法を解説します。「もしかして、交換しなくても延命補強できるのでは?」という選択肢として読んでいただければと思います。
現地調査をして鉄骨土台の目視で診断

鉄骨土台は建物の構造を支える部分であり、腐食が進行すると設備全体の支持力が低下して人的被害にもなりかねません。ニュースや新聞でも錆びトラブルで事故が起きたことを見聞きされていると思います。
しかし、多くのオーナー様にとって、建物の築年数や現状を踏まえたときに、全面交換を選ぶのは現実的ではない思います。なぜなら、全面交換すると建物本体よりも長寿になってしまうって本末転倒になるからです。ほか、長年の運営で鉄骨に配管や樋などが絡み合っており、簡単に撤去や再設置が難しいというご事情もよく伺います。

現場調査を行う際には、鉄骨の劣化状況を把握するために目視や触診によって現状を確認します。これにより、補強可能な範囲を見極めて今後の利用事情を踏まえた延命補強プランをオーナー様にご説明してご理解を得ます。
ベランダや廊下、階段の鉄骨は一部が下地として使われていることがあり、鉄骨全体が外からは見えないため、腐食に気づかないまま長年が経過していることも少なくありません。
丸ごと交換ができない3つの理由と葛藤?
現地でオーナー様からお話を聞いていると、鉄骨土台の全面交換が難しい主な理由はおおよそ下記3点です。(ほかにも、オーナー様ごとに細かいご事情がありますが)
- 周辺設備との干渉により物理的に撤去、交換ができない
- すでに生活設備として使っているので交換中の生活に難儀する
- 費用対効果を考慮し、丸ごと交換に踏み切れない
上記のような事情を理解したうえで、現場ではオーナー様との打ち合わせを通じて、補強の必要性と制約条件を丁寧に共有しながら施工方針を固めていきます。
ほぼすべてのオーナー様は「どこかに相談するまでに葛藤している経緯」があるので、現地でのお打合せではこの葛藤の部分を共有していくことが大切です、錆び状況や計測よりもこの葛藤を把握することの方が大事だ言って過言ではないです。その理由は、いくら優れた工事をししても、それがオーナー様の葛藤を解決していないとお金をかけた意味がないからです。
交換ではなく補強を選ぶことで、得られる耐久年数や強度には一定の制限があるものの、施工コストを大幅に抑えることができます。このバランスを取りながら、補強の目的を明確にし、建物全体の寿命を延ばすための現実的な選択として、多くの現場で実施されています。
具体的な土台鉄骨の補強工事の流れ

ここからは工事例の紹介です。ベランダ床材の撤去後の写真です。
床材を撤去することで下地となっている鉄骨が露出し、腐食の進行具合を詳細に確認できるようになります。特に排水経路の近くなどは、予想以上に損傷が進行しているケースが多く、経験が踏まえた適切な判断が重要になります。劣化が進み再利用が困難な鉄骨部分は撤去し、比較的状態の良い箇所には溶接による補強や部分交換を施します。


比較的強度が健在な鉄フレームを再利用しながら、現地判断で部分交換と溶接固定を繰り返しながら適切な補強作業を進めます。

主要な補強材料は既存鉄フレームの同等規格品が基本ですが、より延命効率の高い規格品に修正しながら補強していくのも施工店の腕の見せ所です。

補強作業が完了した後は、エポキシ防錆材とウレタン塗膜による三層のコーティング処理を実施します。使用材料としては、日本ペイントの「ファインウレタンU100」を採用しており、防錆性と耐候性に優れた仕上がりが特徴です。
ウレタン塗膜の上位塗膜としてシリコン塗膜やフッ素塗膜がありますが、延命補強という視点で見たときにコストパフォーマンスとして一番優れているのはウレタン塗膜と思います。
参考:日本ペイント ファインウレタンU100を使用しています
安全性、耐久性を復活させる要素は多い

新しい床材の設置後は鉄骨部分が再び隠れてしまうため、施工中および施工後に点検を丁寧にに実施して隠れた部分の安全性を確保します。施工後の鉄骨土台は、設備の耐久性を保ちながら、居住者様の安心を支える存在として今後も活躍してくれます。
鉄骨の補強工事は単なる補修作業ではなく、居住空間全体の安全性を担保するための重要な取り組みです。補強材の選定、溶接作業精度、塗装前の下処理、適切な塗装。そして将来起こりそうな事故リスクの想定とその対応策まで、考えることはたくさんあります。
鉄骨の補強工事に関するご質問や相談がありましたら、当社にお気軽にお問い合わせください。営業マンではなく専門のスタッフが親身に対応いたします。
要約Q&A
Q:交換ではなく延命補強という可能性はどう導くのか
A:これまでのメンテナンス履歴と、現状の錆びダメージ、そして今後の維持年数を天秤にかけながら延命の可能性を探っていきます
Q:どれだけ長く延命できるのか
A:延命補強は基本的に「既存の鉄骨」を残しながら行う工事なので、強度の一部を既存鉄骨に依存しなくてはいけません。早め早めのケアを心掛けることで延命期間を延長できると言えます
Q:鉄部塗装の塗り替え時期は?
A:シチュエーションによりますが、おおよそ8年前後です
Q:塗装の色や床デッキの色は変更できるのか
A:変更できます。ただ、塗装色はあまり明るい色を選ぶと既存鉄骨からの錆垂れが目立ってしまうので「錆び色に近いチョコレート色が(外観維持として)無難です」とお答えすることが多いです。色による延命効果に差はありません。
参考:貯水槽鉄骨架台の錆び対策、地震対策