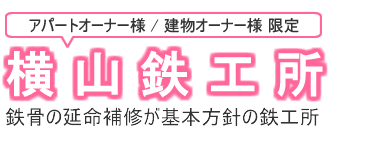この記事を読んでいただきたい方:
建物などの鉄骨耐用年数(法定耐用年数)のような数値ではなく、「実際どうなの?」というリアルな数値で鉄骨階段や廊下の鉄骨寿命について書いた記事です。耐用年数をどう見ればいいのか?耐用延命の方法はどうすればいい?という疑問にお役に立ちます。
目次
階段鉄骨の「リアルな寿命」耐用年数

日々の生活で「階段」や「廊下」を使わない日はありますか?ないと思います。それぐらい「あって当たり前の設備」ですよね。ある日ふと鉄錆び腐食に気づいて心配になったりしませんか?
鉄骨階段や外廊下の耐用年数は、条件付き(メンテナンス頻度・使用状況・鋼材選定など)ながら「実質40年」が最初の寿命ポイントです。これは多数の工事経験からのリアルな統計からです。
建物の法定耐用年数とは違う視点で考える必要があります。なぜかというと、鉄骨階段や廊下などで使われる鋼材は肉厚4mm以下であることがほとんどなので、法定的な視点で見るとその寿命は19年~30年くらいと換算できます。
そして、40年放置している(補修したことがない)階段と、10年ごとにメンテナンスをしてきた階段では強度に雲泥の差ができます。放っておけばおくほど復旧費用は高額になってしまうので、長く使うものだからこそ維持費用を節約しながら安全を確保したいですよね。
鉄骨(無塗装)は放置してると10年~15年くらいが寿命

例えば、鉄骨を塗装が剥げたまま数年放置していると15年後には使いものにならなくなるでしょう。アパートで提供している階段であれば人的被害(事故)に直結します。賠償責任をともなうトラブルになっているオーナー様からご相談を受けたこともあります。※階段(廊下)は建物の一部なので減価償却に含まれ、その原価は工事費用(資材や人件費、ほか諸経費、税金など)になります。
もちろん、建築工事において無塗装で完了する鉄骨工事はないので、工事当初に仕上げ塗装までしていればボロボロにはなりませんが、その後の定期的なメンテナンスをしていれば鉄骨設備は半世紀以上使えます。ひとつの目安として「塗装の機能寿命8年前後」を補修の節目として管理していくと運営費用に損が出ないです。
また、当社は築30年から40年くらいのアパートオーナー様から鉄骨補強の御相談をいただくことが多く、その錆び腐食状況もいろいろです。錆びて強度トラブルが始まるまでの時間の流れは下記のようであることが多いです。
—鉄骨が錆びてボロボロになる流れ—
(1) 鉄部表面にサビ発生(数年経過レベル)
↓
(2) 表面のサビが拡大、同時に鉄骨の内部に浸食(7年前後経過レベル)
↓
(3) 鉄骨強度が徐々に失われる(7年前後経過レベル)
↓
(4) 構造部のサビ穴が空くなど、人的被害リスクが発生し始める(10年以上経過レベル)
※お問合せをいただくタイミングは(2)~(3)の段階が多く、延命対策必要です。
※(4)では怪我など事故を抑止する補強工事が求められます。
(1)の鉄部表面のサビくらいであればオーナー様ご自身でDIY修理することもできるかもしれません。しかし、門扉や手すりなどは、パイプ形状であることが多いのでサビ腐食が発生したら数年でボロボロになります。
厄介なのは「サビは内部から発生するので気付きにくい」という点です。目に見えて穴が空いたときは、内側は真っ赤に錆びています。っと見た印象で「小さなサビ穴」でも、その鉄部の内側では広範囲に腐食が進んでいます。
鉄骨廊下の床面崩落事故から耐用年数を考える
平成28年10月6日、北海道で衝撃的な事故が起きました。アパート外廊下の鉄骨腐食によって、床の一部が崩落。怪我人が出た事件です。
参考:(朝日新聞)アパート外通路の床が抜ける 函館、警官6人転落し負傷
引用画像:函館新聞より

上記の事故の原因は、定期的なメンテナンスを怠った鉄骨劣化が原因です。老朽化した廊下の鉄骨が日常的にかかる荷重に耐えられなくなり、一部が瓦解したのだと考えられます。この現象は鉄骨の塗装工事だけしていても起こり得ます。鉄骨自体のサビ補修が前提です。
廊下崩落事故の原因について考察

以下のようなことが原因として考えられます。
・床面を支える「胴差し鉄骨」の強度ダウン?
・床面の下地となる「デッキプレート」の強度ダウン?
・そのほか、周辺の構造鉄骨部の強度ダウン?
これらの発生源は「床面から浸水する雨水」である場合がほとんどです。雨水の犠牲になる「胴差し鉄骨(廊下の外周部)」や「テッキプレート(廊下の床を支える鉄板)」は下記の工事例のように対処できます。
参考:胴差し鉄骨に大きな腐食ダメージがある場合の補修工事
参考:廊下やバルコニーのデッキプレートが劣化した場合の補修工事
参考:廊下への雨水侵入を防ぐタキストロン工事
消費者庁でも警鐘。鉄骨サビ腐食を「数字で見る」
平成28年3月に消費者庁が賃貸物件における「生命に危機をおよぼす不具合の発生」でも、オーナー様に注意を呼び掛けています。
引用画像:消費者庁「NewsReleaceより」
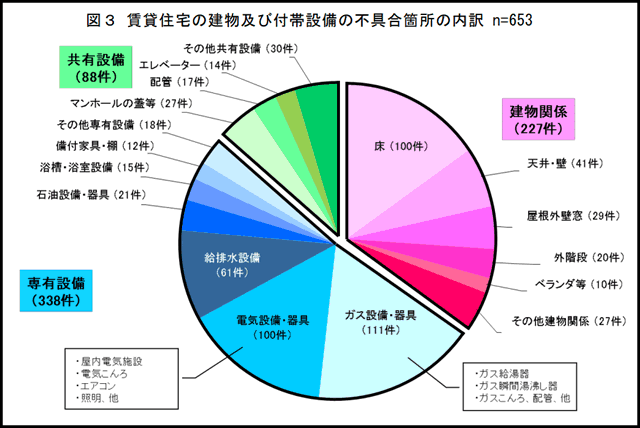
消費者庁に寄せられた不具合情報(653件)のうちの、鉄骨階段の不具合だけで20件にも及んでいます。報告のないものも含めれば、水面下で多くの鉄骨腐食の問題が起きています。アパートの建築ラッシュが30年くらい前にありましたが、この頃の鉄骨設備がメンテナンスを必要としている可能性があります。
鉄骨の耐用年数は「延命」できる!

築30年くらいの木造アパートがあったとします。このアパートに鉄骨製の外廊下と外階段があるとします。塗装工事を怠って10年以上放置していると危険信号です。まだまだ使える!と見た目で油断しないでくださいね。
修理や補修工事を考えたとき、アパートの階段や廊下をそっくり取り換えることは現実的では無いです。すでに入居されている方たちの生活動線となっているからです。
鉄骨の耐用年数を正確に数値化することは難しいです。しかし、よっぽどの腐食ダメージでない限りは寿命を伸ばす工事ができます。そして、定期的な鉄骨サビ対策(=鉄骨サビ補修、塗装コーティング、雨水対策など)を行っていれば、建物本体よりも長生きできるといっても過言ではありません。
「鉄骨の危険段階」を見極めるポイントとは
外階段や外廊下の危険段階を見極めるポイントはどこでしょうか?
※ここの記事はsuumoジャーナルさんに寄稿しています
手摺や門扉、目隠しパネルのような小さな設備であれば比較的簡易に修理できますが、鉄骨廊下のような大きな設備である場合「胴差し鉄骨(廊下の外周を囲う鉄骨)」に大きなサビ穴が空いていると要注意です。つまり、廊下の床面を支える強度に問題が発生しています。
以下の写真が「危険な胴差し鉄骨」の代表例です。

また、鉄骨階段であれば「ササラ桁」が重要な部分となります。このササラ桁の強度が健在であれば比較的安価で危険回避できることが多く、補強工事で耐用年数を伸ばすことができます。ササラ桁に強度が全く期待できない場合は黄色信号です。

鉄骨の耐用年数について記事を書いてみました。いかがでしたでしょうか。
経験上、当社で診断に伺って「あぁ・・これはもうダメだ。交換しかない」という判断に至る鉄骨設備は1割を切る程度です。
オーナー様、あきらめてしまう前に、鉄骨の耐用年数の延命をご検討ください。経験30年以上の職人が現地を直接診断します。鉄骨延命の策はお気軽にご相談ください。
参考記事:鉄骨階段の寿命は40年目が節目。延命方法とは。