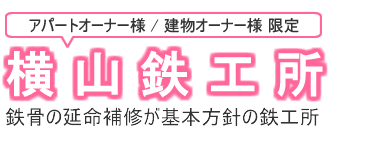この記事を読んでいただきたい方:
所有するアパートや自宅の鉄骨階段の床(縞鋼板)が錆びて、歩くと「きしむ」「フワフワする」など、安全面に不安を感じているオーナー様。高額な交換工事を勧められたが、ひとまずの補修工事で安全性を確保できないか調べているオーナー様に向けた記事です。

目次
交換工事だけが正解ではない

鉄骨階段が錆びてボロボロになったとき、多くの業者さんは「交換」を勧めます。もちろん正解です。ただ、必ずしもそれが最適解とは限りません。
建物の寿命を超える鉄骨階段は、安全面ではクリアされても、運用面では「?」です。
弊社は、「建物の寿命に見合う延命補修ができないか」を追求する鉄工所です。つまり「安全性を重視しつつ、コストを最小限に抑える」というスタンスです。コストを節約することのデメリットもあります。下記のページをご参照ください。
参考:鉄骨階段の延命補修で達成すること、されないこと
現地調査:腐食の進んだ縞鋼板

調査に伺ったのは都内のアパートです。「だいぶ放っておいてしまって、階段がボロボロになってしまって・・」とオーナー様。一見すると目立つサビはありませんが、近づいてみると以下のような状態でした。


- 階段の段板(縞鋼板):塗装が剥げ、サビが進行。踏むときしみ・沈みを感じる
- 踊り場(昇降途中の平場):腐食が進み、鉄板が痩せて穴が空いている
入居者様からも「抜け落ちそうで怖い」というお声もあったそうです。
補修の考え方:「痛くない歯の治療」

経年の鉄骨設備の補修工事では、既存の構造体に余計な負担をかけないことが重要です。
理由はシンプルで、腐食に蝕まれている鉄骨設備に対して、新築時のような強めの工事をすると、比較的健全な鉄骨の部分まで傷めてしまうからです。「痛くない歯の治療」のようなものです。
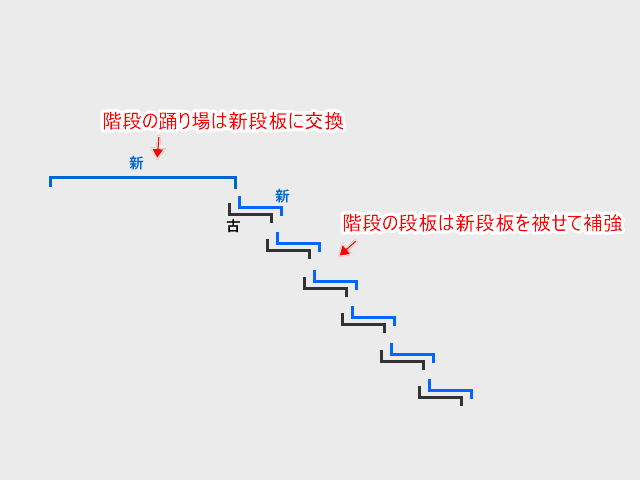
そこで、今回の補修工事では、下記のように進めます。
- 段板 → 既存を外さず、上から新しい縞鋼板を溶接
- 踊り場 → 腐食が激しいため、下地鉄骨を補強したうえで板を交換
まず、既存の段板(縞鋼板)は外さずそのままにして、上から新しい段板を被せて溶接します。理由は「段板を支える梁(ササラ桁)も弱っていたので余計な工事負荷を与えないため」です。階段全体の強度バランスを見極めつつの、慎重な判断ポイントです。
踊り場の床を支える下地フレームの補強も必要であるため、床板を外して下地フレームを補強のうえ、床板の交換という判断をしました。
実践:補修工事 ~段板~

既存の段板にケレン(鉄骨表面に付着したサビを削り取る作業)をかけて、防錆塗膜をします。工事後には隠れてしまう部位なので、しっかりと下処理をします。

既存の段板の上に、新しい縞板段板を乗せて溶接します。これで、既存の骨組みに負荷を与えず、安全性を回復しました。

ちなみに、既存の手摺部位にドリルで小さな穴をあけると、水が勢いよく飛び出すことがあります。これは鉄パイプの中に溜まっていた雨水(錆び水)や泥水です。
実践:補修工事 ~踊り場~

踊り場の床板を解体します。これまで床を支えていた下地フレームを露出させた状態です。下地フレームにも強い腐食があるため、このタイミングで補修(部分交換、増設など)をします。

下地フレームの補強が終わったら、新しい床縞鋼板を溶接。

最低限、必要な部分だけを交換にして、ほかは補強などして既存骨格を再利用します。新築と比べれば強度は落ちますが、歩行の安全性は復旧されています。
実践:補修工事 ~塗膜コーティング~

鉄骨補修工事が終わったら、補修効果の維持が目的の鉄部塗装をします。鉄部塗装の役割は単に「色が付く」のではなく、鉄骨の酸化要因(湿気)を抑止する役割があります。
弊社では、2液エポキシ防錆1層、ウレタン塗膜2層でコーティングします。
参考(エポキシ防錆):日本ペイント ハイポンファインプライマー
参考(ウレタン):日本ペイント ファインウレタンu100

常に雨風に晒される屋外の鉄骨設備は、腐食リスクを常に負っているわけですが、厚い塗膜が付くことで外気から鉄部を守り、腐食リスクの大幅に軽減してくれます。
適切な定期メンテナンス(7年前後を軸に)をしていけば、この階段は、あと15~20年ほどの延命が可能です。
工事完了:費用は交換の3分の1でした

延命工事が完了した写真です。工事前の写真と同じように見えますが、中身は大きく異なります。
オーナー様には下記のメリットでお役に立ちました。
- 工期短縮(居住者様の負担を最小限に)
- 費用は交換の約1/3(ケースバイケースですが)
- 安全性を確保しつつ15年以上の延命
補修工事は条件を選ぶ作業ではありますが、入居者様のご迷惑(階段歩行できない日がないまま生活できた)を最低限に、工事金額も抑えて、しかも短納期。延命補修がひとつの選択肢ととしてオーナー様のお役に立てれば幸いです。
鋼製設備のメンテナンスでお困りのオーナー様、お気軽にご相談ください。
また、参考までに「段板をそっくり交換する工事」も行いました(下記)
要約Q&A
Q:鉄骨の延命補修を短納期、低コストにできる仕組みは?
A:既存構造を残して作業をすることで使用鋼材量を減らし、優先順位を絞って作業することで人件費を節約しています
Q:工事中、居住者は階段を使えるの?
A:はい、使っていただけます。安全のため、作業中はお声をかけていただければ作業を停めてご誘導します
Q:鉄骨階段の床がきしむ・フワフワするのは危険ですか?
A:はい。その現象の原因は、床の鉄板の腐食か、あるいは床を支えている下地フレームの腐食か、もしくは両方か、です。腐食で強度が落ちると抜け落ちるリスクもあるため、早めの点検が必要です。
Q:他社からは「交換工事」を勧められており、どっちがいいのかわかりません
A:交換工事は根本から解決する工事です。補修工事は現状をそのまま使って延命する工事なので、交換工事ほどの寿命にはなりません。歯でいうと「インプラント」か「銀歯を被せる」かの違いです?
Q:補修では交換と比べて安全性が落ちませんか?
A:はい。交換工事は鉄骨設備が刷新されるので安全性に優れます。弊社が行うのは延命を追求するもので、利用に支障がないレベルで維持をするのが目的です。建物の残存寿命に合わせた「コスパの良い解決策」といえます
Q:補修後はどれくらい持ちますか?
A:今回の階段は、その後も定期メンテナンス(7年前後)をしていくことで、15~20年の維持が期待できます。鉄骨補修工事後のメンテについてのガイド記事もあるのでご参照ください